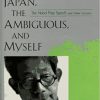外国語を習得したい方にも、ある専門分野について理解を深めたい学生にも、常に「多読」をお勧めしています。
しかし、そこでストップしないで欲しいのです。
自分が読んだこと(あるいは自分が聞いたこと)を、「要するに、こういうことでしょうか…」などと言って、他の人に説明してみることも、常にお勧めしています。
と言いますのは、あるインプットについて考え、自分の言葉で言い直すという作業、あるいは書き直すという作業を行わなければ、人は自分の理解度を測る(あるいは測ってもらう)ことができません。
要するに、ある物事を理解するのに、次のような作業が不可欠です。
- 他者の言葉を誠実に読んでみる。聞いてみる。
- その言葉の意味について考える。理解してみる。消化してみる。
- 自分自身が考えた比喩や例話を使いながら、別の言葉で表現してみる。説明してみる。
- 自分の説明の正確さや適切さを測ってみる。または、自分よりもそのことについて理解している人に測ってもらう。
- 不十分なところがあれば、インプットとアウトプットの循環をくり返す。
前回は、このような作業を奨励している「ファインマン・テクニック」という勉強法をご紹介しました。まだご覧になっていない方は、ぜひ、この短い記事をご参照ください。
今回は、基本的に同じ作業を奨励している池上彰氏の言葉をご紹介したいと思います。
『考える力がつく本』の中で、「考える力を効率的に身につける方法」という項目で、池上氏はこういっています。
インプットは大事です。ただ、やみくもにインプットを増やしても、「考える力がつく」とはいえません。私は本が好きで、大学生のときは岩波文庫の目録を見て全部読み尽くしたいと思っていました。本を読むとほっとしていたし、読書は絶対に勉強になると思っていました。ところが、ドイツの哲学者ショーペンハウエルの『読書について』を読んで、頭を殴られたような衝撃を受けました。
ショーペンハウエルは、次のようにいっています。
「読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆書きの線をペンでたどるようなものである。だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。自分で思索する仕事をやめて読書に移る時、ほっとした気持ちになるのも、そのためである。だが読書にいそしむかぎり、実は我々の頭は他人の思想の運動場にすぎない」(斎藤忍随訳)
本を読んで賢くなったつもりになっていても、それは自分で、モノを考える力がついたのとは違うということをいっているのです。
ショーペンハウエルはかなりの毒舌家だと知っていましたが、ショックでした。
しかし、こうもいっています。
「だが熟慮を重ねることによってのみ、読まれたものは、真に読者のものとなる」
これを読んで私は、本を読むということは、いってみればザルで水を汲むのに似ているのだなと自分で勝手に解釈しました。読んだあとは、なるほどとわかった気になるけれど、すぐに水(知識)はザルの網目からこぼれてしまう。つまり忘れてしまう。大量に読んだり、熟慮を重ねて何回も読んだりしていれば、少しずつでも水はたまる。読書とは、そういうものかもしれないと思いました。(16–17頁)
しかし、正直に言うと、これで終わってしまえば、かなりがっかりしてしまいます。
そこで終わりません。池上氏はこの項目でこう結論しています。
アウトプットは、インプットの力を引き出すのです。そこで、読者のあなたに提案です。「知識が身についたかな」と思えば、ぜひそれを誰かに伝えてみてください。
実際に伝えてみようとすると、きっと思いのほかうまくいかないはずです。そこで「なぜだろう」と考える。必要だと思えば、さらに周辺情報を調べていく。たぶんこれが重要なのです。(20頁)
どんなことであれ、何かについて知りたい、理解したいのであれば、適切なインプット源を見つけ、自分なりのアウトプット源に練り変えてみるしかないかも知れません。
大変な作業だと思ってしまえば、苦しくなるでしょう。しかし、この作業自体に価値がある、知性が豊かになる、考える力が身につく、などと思えば、物事を理解するという目的以上に、インプットをアウトプットに作り変えるという手段が楽しくなるでしょう。
***
スポンサーリンク